| items per Page |
|
『稲妻のたたら砂エリアに存在しうる重大な歴史事件についての簡単な分析』

 | Name | 『稲妻のたたら砂エリアに存在しうる重大な歴史事件についての簡単な分析』 |
| Type (Ingame) | 任務アイテム | |
| Family | Non-Codex Series, "A Brief Analysis of Possible Events of Historical Importance in the Tatarasuna Area" | |
| Rarity | ||
| Description | 『稲妻のたたら砂エリアに存在しうる重大な歴史事件についての簡単な分析』 |
説明:本論文は因論派の支援プロジェクト『ベールをはずして』に属する作品であり、番号は追加待ちである。 作者:アカバ 要旨:稲妻たたら砂エリアは稲妻の製錬鍛造業の重要な場所の一つと考えられてきた。このエリアでは事故が二回発生している。そのうちの一回目に関する記録はどれも曖昧なものである。たたら砂エリアでの最初の事故の裏には人知れぬ歴史的な要因があるのではないか、と筆者は考えている。本論文は既知の資料をもとに、この事件を分析してみるものである。 キーワード:たたら砂エリア、雷電五箇伝、御輿長正、傾奇者 はじめに:本論文は筆者の恩師であるルミ先生のレポート『たたら砂エリアに秘匿された疑いのある人文的故事』を受け継ぎ、展開し、この研究を引き続き進めたいとするものである。資料によると、稲妻の鍛造技法はもともと雷神——雷電将軍から受け継がれたものだそうだ。職人たちは神の技術を受け継ぎ、それを製錬鍛造業に応用した。だが、鍛造製錬業の核であるたたら砂エリアには、雄渾たる鍛造業にふさわしくない不思議な噂がある。御輿家、丹羽家、そして奇妙な人形——この三者が切り口となり、我々はそこからたたら砂の裏に隠された真実を垣間見ることができるようになった。 本文 たたら砂エリアにあった奇妙な紙切れに、こんなことが書かれている—— 1 「……僭越ながら私は、長正様が刀鍛冶をするのは彼の心境に良い影響を与えると考える……」 「……『御輿』の汚名をそそぐことに執着するのは、実に気力を消耗する……」 「……それと、桂木様が名椎の浜を見回りしていた時、名無しの傾奇者を見つけた……」 2 「……目付様は玉鋼錠をいくつか買った……」 「……造兵司佑様、そして桂木様と夜通し鍛冶の心得を話していた。」 3 「……やっと長巻の一振りを造り出せた。その名は『大たたら長正』……」 「……目付様も非常に喜んでいる、造兵司佑様と……」 「……望は『大たたら長正』の美しさに感動し、それのために絵を描いた……」 「……浮浪の傾奇者と剣舞を舞った……」 4 「……傾奇者も行方不明になった……」 「……目付様は怒り、桂木を斬った。その切れ筋は、まさに大業物…そして、自ら作った長巻をたたら炉に捨てた……」 「……望はそれに不満を抱き、燃え溶けた刀を取りに行き……大やけどをした……」 5 「……望はその夜死んだ……桂木様は職責を汚したとはいえ、すべて善意からのものだったと思う……」 6 「……金次郎は長巻と望の描いた絵を武器庫に隠した……」 「……長正は厳しいが、白黒をはっきりさせる性分だ。しかしそれは同時に、非情でもあるということ。彼は自らの家名の潔白にこだわっており…私もたたら砂の人たちも、彼の母である千代のことで目を曇らせることなく、長正のことを信じている……」 「……彼と共に『大たたら長正』を作った喜びを忘れたくない。あの夜に、名無しの傾奇者、桂木と剣舞を舞った喜びも……」 7 「……撤退する時、武器庫の鍵を三つに分け、一つは目付様に、一つは造兵司正様に、一つはたたら砂に残し、賊の侵入を防ごうとした。」 「しかしあまりにも慌ただしかったため、目付様と造兵司正様を見つけられず、三つの鍵をすべてたたら砂にある三つの宝箱に隠すしかなかった……」 上記の7枚のメッセージはたたら砂エリアに散らばっている。そのうち、6枚は耐久性に優れた紙に記録されており、いずれも非常に古いものと思われるが、最後の1枚だけがやや新しいようだ。筆者は、6枚の紙と最後の1枚は異なる時代のものであると思っており、その年代の差を検証する必要がある。また、6枚の内容は互いに関連しているため、同じ出来事を指しているはずである。 ルミ先生は『たたら砂エリアに秘匿された疑いのある人文的故事』(以下、『人文的故事』と略称)の中で、スメールの学者が稲妻にたたら砂一帯の人文史を研究しに行っていたということに触れている。ルミ先生が『人文的故事』を書いた当時、たたら砂は一連の事件ですでに衰退した状態だったが、筆者が本文を書いた時分よりはましであった。たたら砂の最も中心的なエリアは、今は全く居住に適しておらず、住む人も確かにいない。住民たちは海辺に移り、水辺に住むようになっていた。スメールの学者たちは、彼らからこのようなことを聞いた——かつてたたら砂はとても繁栄しているところだったと。数百年前、まだ黄金時代と呼べる頃、たたら砂は造兵司正の丹羽、造兵司佑の宮崎、そして目付の御輿長正に管理されていた。同時に、年配の人たちや、より歴史ある家系の人たちは、たたら砂には奇妙な噂があったと繰り返し強調していた。 噂はほとんど「妖怪」にまつわるものであり、稲妻の特色に溢れていた。しかし、そのうちごく一部の中で、「人形」という単語の言及があったのだ。注意すべきは、人形それ自体は伝統的なものであり、ありふれた稲妻の妖怪ではないことだった。学者たちは疑問を感じ、それについて追及した。そして、次のような情報が得られた。 -かつてたたら砂に、とある人形が現れた。その見た目は秀麗で、きちんとした身なりをしており、体にある特殊な関節の痕跡を隠すことを知っていた。たまに誰かが口にしなければ、それが人形であることは分かりにくい。それに、人形特有の関節の痕跡は時間が経つにつれて薄くなっていっていたようだ。最後には見えなくなり、完全に人間の姿になるかもしれない。 -その人形の名前を知る人はほとんどいない。人々はそのような人形がたたら砂に出没していたということを知っているだけだ。中心地でそれを見た人もいれば、浜辺で見た人もいる。伝説では、人形は海辺に佇み、海の向こうの稲妻城を見つめていたようだ。そこに何があるのか、また人形が何を見つめていたのか、誰も知らない。 前述したように、6枚の紙切れのには「名無しの傾奇者」のことが書いてある。傾奇者とは、稲妻において変わった身なりをしたり、常識を逸脱した行動に走る人を指すことが多い。そのため、このような人物が印象に残るのは当然といえば当然といえる。もしたたら砂に本当に人形が存在し、そのうえで恐慌を起こしたりなどしていないなら、妖怪と人間が共生する稲妻の社会形態を考えると、当時人形はたたら砂の地元住民の一人になっていた可能性が高い、と筆者は考える。そして関連記録が少なく、あまり知られていない「傾奇者」とは、人形のもう一つの呼び名かもしれない。服装があまりにも華麗で独特であるなら、人々はその人の他の特徴にあまり目を向けなくなる。この推測にはまだ強力な証拠が必要だが、一つの考え方として残しておくことはできる。 筆者は稲妻の関連資料に基づき、たたら砂と関連があるかもしれない一部の人物を整理した。管理者から順に、記録は以下の通りである—— 造兵司正——丹羽 フルネームは丹羽久秀、一心伝丹羽家の後継者。その一族は赤目、楓原と共に一心三作と呼ばれている。記載によると、丹羽は謙虚で聡明、土地と民生を管理する優れた人材であった。のちに彼は行方不明となっており、家族を連れて事故後のたたら砂を離れたと思われる。 造兵司佑——宮崎 フルネームは宮崎兼雄、丹羽の補佐。出身は不明。主に鍛造及び人員管理において、丹羽をサポートするなどしていた。穏やかで優しい人物であり地元に友人が多く、御輿長正とも親交があった。 目付——御輿長正 御輿家の後継者、鬼族の武者御輿千代の養子であり、「胤の岩蔵」御輿道啓の養弟である。母の千代が行方不明になった後、養兄の道啓に捨てられた。彼は一人で一族すべての責任を背負い、家族の汚名をそそぐために日々奮闘していた。様々な資料によると、御輿長正はやや頑固な一面はあるが、剛直で品行の正しい人であったとされる。紙切れの記録によると、彼は修身のために刀の鍛造を習い、わざわざ宮崎の教えを受けていた。名刀大たたら長正を鍛え上げた後、彼はあることから部下の桂木を斬った。 部下——桂木 フルネーム、出身ともに不明。筆者は多くの資料を調べたが、桂木本人に関するさらなる情報を得ることはできなかった。彼は御輿長正の手下であり、忠実な武人だった。御輿長正に救われたため、長正のために水火も辞さないとを誓ったとされる——随従することから、命を捧げるまで。 傾奇者 フルネーム、出身ともに不明。筆者は多くの資料とルミ先生の見解を合わせ、この人物こそ噂の奇妙な人形であると推測している。伝説によると、傾奇者は見た目が非常に美しく、穏やかで優しい性格の持ち主だという。『人文的故事』によると、彼は桂木によってたたら砂に連れてこられ、地元住民の一人となったそうである。傾奇者がたたら砂に来たばかりのころ、服を洗うことも料理を作ることもできず、細かい仕事は一切できなかった。地元の人たちが丁寧に教えたため、洗濯、舞踊、そして小物を鍛造する方法などを身につけるようになった。紙切れの記録によると、『大たたら長正』が鍛え上げられた時、傾奇者もその場にいた。だが、御輿長正が桂木を斬る直前で傾奇者に関する手がかりは途切れている。筆者は、傾奇者——すなわち人形は、桂木の死と関係している可能性が高いと考える。 (残りの部分はどうやらまだ書き終わっていないようだ…でも、これがかなり工夫された論文であることは確かだ。) |
『稲妻のたたら砂エリアに存在しうる重大な歴史事件についての簡単な分析』

 | Name | 『稲妻のたたら砂エリアに存在しうる重大な歴史事件についての簡単な分析』 |
| Type (Ingame) | 任務アイテム | |
| Family | "A Brief Analysis of Possible Events of Historical Importance in the Tatarasuna Area", Non-Codex Series | |
| Rarity | ||
| Description | (test)学者论文后 |
説明:本論文は因論派の支援プロジェクト『ベールをはずして』に属する作品であり、番号は追加待ちである。 作者:アカバ 要旨:稲妻たたら砂エリアは稲妻の製錬鍛造業の重要な場所の一つと考えられてきた。このエリアでは事故が二回発生している。そのうちの一回目に関する記録はどれも曖昧なものである。たたら砂エリアでの最初の事故の裏には人知れぬ歴史的な要因があるのではないか、と筆者は考えている。本論文は既知の資料をもとに、この事件を分析してみるものである。 キーワード:たたら砂エリア、雷電五箇伝、御輿長正 はじめに:本論文は筆者の恩師であるルミ先生のレポート『たたら砂エリアに秘匿された疑いのある人文的故事』を受け継ぎ、展開し、この研究を引き続き進めたいとするものである。資料によると、稲妻の鍛造技法はもともと雷神——雷電将軍から受け継がれたものだそうだ。職人たちは神の技術を受け継ぎ、それを製錬鍛造業に応用した。だが、鍛造製錬業の核であるたたら砂エリアには、雄渾たる鍛造業にふさわしくない不思議な噂がある。御輿家、丹羽家、そして外国から訪れた奇妙な機械職人——この三者が切り口となり、我々はそこからたたら砂の裏に隠された真実を垣間見ることができるようになった。 本文 たたら砂エリアにあった奇妙な紙切れに、こんなことが書かれている—— 1 「……僭越ながら私は、長正様が刀鍛冶をするのは彼の心境に良い影響を与えると考える……」 「……『御輿』の汚名をそそぐことに執着するのは、実に気力を消耗する……」 2 「……目付様は玉鋼錠をいくつか買った……」 「……造兵司佑様、そして桂木様と夜通し鍛冶の心得を話していた。」 3 「……やっと長巻の一振りを造り出せた。その名は『大たたら長正』……」 「……目付様も非常に喜んでいる、造兵司佑様と……」 「……望は『大たたら長正』の美しさに感動し、それのために絵を描いた……」 4 「……目付様は怒り、桂木を斬った。その切れ筋は、まさに大業物…そして、自ら作った長巻をたたら炉に捨てた……」 「……望はそれに不満を抱き、燃え溶けた刀を取りに行き……大やけどをした……」 5 「……望はその夜死んだ……桂木様は職責を汚したとはいえ、すべて善意からのものだったと思う……」 6 「……金次郎は長巻と望の描いた絵を武器庫に隠した……」 「……長正は厳しいが、白黒をはっきりさせる性分だ。しかしそれは同時に、非情でもあるということ。彼は自らの家名の潔白にこだわっており…私もたたら砂の人たちも、彼の母である千代のことで目を曇らせることなく、長正のことを信じている……」 「……彼と共に『大たたら長正』を作った喜びを忘れたくない……」 7 「……撤退する時、武器庫の鍵を三つに分け、一つは目付様に、一つは造兵司正様に、一つはたたら砂に残し、賊の侵入を防ごうとした。」 「しかしあまりにも慌ただしかったため、目付様と造兵司正様を見つけられず、三つの鍵をすべてたたら砂にある三つの宝箱に隠すしかなかった……」 上記の7枚のメッセージはたたら砂エリアに散らばっている。そのうち、6枚は耐久性に優れた紙に記録されており、いずれも非常に古いものと思われるが、最後の1枚だけがやや新しいようだ。筆者は、6枚の紙と最後の1枚は異なる時代のものであると思っており、その年代の差を検証する必要がある。また、6枚の内容は互いに関連しているため、同じ出来事を指しているはずである。 ルミ先生は『たたら砂エリアに秘匿された疑いのある人文的故事』(以下、『人文的故事』と略称)の中で、スメールの学者が稲妻にたたら砂一帯の人文史を研究しに行っていたということに触れている。ルミ先生が『人文的故事』を書いた当時、たたら砂は一連の事件ですでに衰退した状態だったが、筆者が本文を書いた時分よりはましであった。たたら砂の最も中心的なエリアは、今は全く居住に適しておらず、住む人も確かにいない。住民たちは海辺に移り、水辺に住むようになっていた。スメールの学者たちは、彼らからこのようなことを聞いた——かつてたたら砂はとても繁栄しているところだったと。数百年前、まだ黄金時代と呼べる頃、たたら砂は造兵司正の丹羽、造兵司佑の宮崎、そして目付の御輿長正に管理されていた。同時に、年配の人たちや、より歴史ある家系の人たちは、たたら砂には奇妙な噂があったと繰り返し強調していた。 筆者は稲妻の関連資料に基づき、たたら砂と関連があるかもしれない一部の人物を整理した。管理者から順に、記録は以下の通りである—— 造兵司正——丹羽 フルネームは丹羽久秀、一心伝丹羽家の後継者。その一族は赤目、楓原と共に一心三作と呼ばれている。記載によると、丹羽は謙虚で聡明、土地と民生を管理する優れた人材であった。のちに彼は行方不明となっており、家族を連れて事故後のたたら砂を離れたと思われる。 造兵司佑——宮崎 フルネームは宮崎兼雄、丹羽の補佐。出身は不明。主に鍛造及び人員管理において、丹羽をサポートするなどしていた。穏やかで優しい人物であり地元に友人が多く、御輿長正とも親交があった。 目付——御輿長正 御輿家の後継者、鬼族の武者御輿千代の養子であり、「胤の岩蔵」御輿道啓の養弟である。母の千代が行方不明になった後、養兄の道啓に捨てられた。彼は一人で一族すべての責任を背負い、家族の汚名をそそぐために日々奮闘していた。様々な資料によると、御輿長正はやや頑固な一面はあるが、剛直で品行の正しい人であったとされる。紙切れの記録によると、彼は修身のために刀の鍛造を習い、わざわざ宮崎の教えを受けていた。名刀大たたら長正を鍛え上げた後、彼はあることから部下の桂木を斬った。 部下——桂木 フルネーム、出身ともに不明。筆者は多くの資料を調べたが、桂木本人に関するさらなる情報を得ることはできなかった。彼は御輿長正の手下であり、忠実な武人だった。御輿長正に救われたため、長正のために水火も辞さないとを誓ったとされる——随従することから、命を捧げるまで。 (残りの部分はどうやらまだ書き終わっていないようだ…でも、これがかなり工夫された論文であることは確かだ。) |
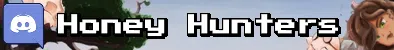



She feels kind of ass.