| items per Page |
|
| Table of Content |
| 荒山孤剣録·一 |
| 荒山孤剣録·二 |
| 荒山孤剣録·三 |
| 荒山孤剣録·四 |
荒山孤剣録·一

 | Name | 荒山孤剣録·一 |
| Type (Ingame) | 任務アイテム | |
| Family | Book, 荒山孤剣録 | |
| Rarity | ||
| Description | 璃月港で流行ってる武侠小説、元素力と錬金術のない世界で起こった愛と憎しみの物語。本巻は金七十二郎の復習の始まりを述べた一冊。 |
| 夜空を切り裂けた剣の閃きは星月の光さえ奪い去る。 荒山に冷たく風の音が立ち、剣と共に舞い上がった。 風雨が止んだ。田舎の道を歩いていたのは一人だけであった。 ちぢれ髪に鷹の鼻と梟の目をした彼は人とは思えない様子をしていた。ふらふらと、細い体で足を運ぶ姿は病膏肓に入る病人のようであった。この山奥においては人間よりもお化けといったほうが相応しい。 彼は三日間何も口にせず、休憩もなく道を歩いた。 三日前、彼にはまだ名声と名剣と落ちぶれた道場があった。けれども今の彼には憂鬱と悲しみだけが、雨と共に彼の額に落ちてくるだけだった。 三日前、無名の剣士が彼の師匠と妹弟子を殺し、高山の雪を真っ赤に染めた。 今、彼は新たな名前を手に入れた——金七十二郎。 同門の七十二人の中で生き残ったのは彼一人だけであった。 —————— どれくらい歩いたのか、後ろから車の音がした。 金七十二郎は身を横に傾け、車に話しかけた。「屠毘荘への車か?」 車夫は頭を頷き、「ここの車はほとんどが屠毘荘を通りかかるだろう。」と言い返した。 金七十二郎はまた聞く。「ならば、そなたの車に人は乗れるか?」 車夫は彼に答えた。「乗れるが、お前を乗せるつもりはないね。」 金七十二郎は車夫の言葉が理解できなかった。「どうせ同じ方向なのに、どうして俺を乗せるのはだめなんだ?」 車夫は言った。「お前と儂を一緒にするな。」 「だまれ。」 金七十二郎の声が聞こえると、車夫はあがく間もなく剣光と共に車から落ち、息絶えた。 金七十二郎という男はまさにこうであった。すべてを失い、度胸まで縮んだが、それでも、彼は繰り言が大嫌いだった。 血にまみれた車に乗り、金七十二郎は屠毘荘へ向かった。 |
荒山孤剣録·二

 | Name | 荒山孤剣録·二 |
| Type (Ingame) | 任務アイテム | |
| Family | Book, 荒山孤剣録 | |
| Rarity | ||
| Description | 璃月港で流行ってる武侠小説、元素力と錬金術のない世界で起こった愛と憎しみの物語。本巻は金七十二郎が初めて屠毘荘についたことを述べた一冊。 |
| 遠い冥思の国で、「屠毘」は幻を解けて、真実に向き合うことを意味する。 屠毘荘は荒山の下にある。ただ一本の道のみ外の世界と繋がっていた——それが金七十二郎が通ってきた道であった。 曇天の下、風が吹き荒ぶ。 仇ができるまで、金七十二郎と屠毘荘の間にはなんの因縁もなかった。 車が荒山の麓についた頃、空はすでに真っ暗になり、黒雲が月を覆い隠していた。金七十二郎も自分の身と心を暗闇に溶け込ませた。 暗闇の中、月の光が荘主を照らしていた。屠毘荘はそれほど大きくはないが、その荘主は決してただ者ではない。荘にいる人たちは荘主の名前を聞く勇気すらなかった。 彼らが知っているのは、荘主が背負っている血の仇とその真っ赤に染まった瞳だけであった。 彼の目は真っ赤に鋭く光っていた。まるで細長い剣のように、人の心を刺すようだった。 彼の人柄もその目のように、いつでも他人を刺し殺せる槍のようであった。 「時間だ。」 荘主は独り言を言った。坊主頭の上には月の光が踊っているようだった。 屋敷の外、一匹の悪鬼が剣を振り荘主の手下たちを切っていた。 屠毘荘は悪の群れが集まる場所であるが、各流派の掟で誰も軽率に争うことができなかった。 しかし、金七十二郎はすでに自身の流派を失っている。掟の縛りを受けない彼は渇いた鬼のように、剣を持って仇の血を求めた。 殺気を纏った風雨が鬼の血を洗い落ちると、すぐにまた血の色になった。 緋色の剣客が緋色の雨の中を歩いた。その体はもう傷だらけになっていたが、彼を防げる者はいなかった。 血の匂いがすべて雨に洗われ、剣客は重い足を運んで荘主の屋敷へ向かった。 —————— 外の殺気がだんだん静まると、荘主は手に持った酒を空中にまいた—— 殺気と共にやってきた古い付き合いを祭るためか、あるいは己の汚い魂を祭るためか。 扉から誰か入ってきた。金七十二郎だ。彼は血の匂いにまみれた緋色の姿をしていた。 「荘主、聞きたいことがある。」 「お前はずいぶんと荘にいる人を殺したな。」 「多からず少なからず、ぴったり三百六十二人だ。」 荘主は何も言い返さなかったが、そのこめかみに浮かんだ青筋は彼の反応を表していた。 「お、それに犬一匹。」 そう言った途端、緋色の影は荘主の前に何かを投げ捨てた。 それは番犬の骨であった。長時間煮たかのように、骨はきれいになっていた。 この一時間で、金七十二郎は荘にいる三百六十二人を殺しただけでなく、番犬まで煮込んでいた。 なんと残酷な! なんと冷血な! 荘主は嘆き、剣を持って彼に向かった。 |
荒山孤剣録·三

 | Name | 荒山孤剣録·三 |
| Type (Ingame) | 任務アイテム | |
| Family | Book, 荒山孤剣録 | |
| Rarity | ||
| Description | 璃月港で流行ってる武侠小説、元素力と錬金術のない世界で起こった愛と憎しみの物語。本巻は金七十二郎と屠毘荘の荘主の対決を述べた一冊。 |
| 雨は止んだが、空はまだ曇ったまま。 金七十二郎は荘主から仇の情報を聞き出した。 そして今、屠毘荘には主のいない空っぽの家と怨念しか残されていない。 いや、この世に幽霊なんていないだろう。 これは元素力がない世界、 当然、亡者の記憶が元素の共鳴を借りて蘇ることもないのだ。 荘主はなかなかの相手であった。彼の剣は鋭くて速かった。金七十二郎の体にはいくつかの深い傷ができていた。 しかし残念ながら、彼の心は遅すぎた。 これは元素力がない世界、 当然、剣法にも元素の加護はない。 剣客は元素ではなく、ただ体力で戦うしかない。 腕を指のように、心を目のように使うのはこの世界で「剣」を使うコツなのだ。 荘主はいい剣客であったが、「心」の重要性を分かっていなかった。 金七十二郎は持っていた欠けた香炉を捨て、重傷になった荘主に向かっていった。 剣客に向かって攻撃することだけに注意力を注いでいた荘主は、相手の左手から繰り出される攻撃に気がつかなかった。 電光石火の刹那、屠毘荘の荘主は香炉に打たれ何回か転り壁にぶつかった。 「卑怯者…」 血まみれの悪党は何も言わなかった。荘主に応えたは風の音のみ。 「…お前が探している者は、この後ろの荒山にいる…自ら死を求めるとはな…」 悪党は去り、彼に応えたは風の音と… 山火事が起きる音だけであった。 |
荒山孤剣録·四

 | Name | 荒山孤剣録·四 |
| Type (Ingame) | 任務アイテム | |
| Family | Book, 荒山孤剣録 | |
| Rarity | ||
| Description | 璃月港で流行ってる武侠小説、元素力と錬金術のない世界で起こった愛と憎しみの物語。本巻は金七十二郎が荒山で遭った危機を述べた一冊。 |
| 虹が消えた頃に、金七十二郎はようやく屠毘荘を出て山へ向かった。 昔の伝説によると、この「荒山」は天帝の刃で切り立てられ、険しい絶壁になっていた。 荒山に地母の涙が沁みているため生物が成長しないという話が民の間で流れていた。 荒山はかつて金に溢れた鉱山で有名だったが、地震でそれらが破壊され、無数の労働者が亡くなった。 それ以降、荒山は猛獣と賊どもに占拠され、誰一人もう一度採掘しようとは思わなかった。 その猛獣と賊の中に、金七十二郎の仇がいた。 剣客は肩を傾け、おぼつかない足どりで歩いていた。この前に屠毘荘主から受けた傷が彼を苦しめた。 この山の奥で自分を獲物として狙う者がいると剣客は知っていた。 長年血にまみれて生きてきた金七十二郎は鋭い勘をもっていた。 一見何もないように見えるが、荒山はすでに金七十二郎に大きい罠を仕掛けていた。 闇に隠れた賊は彼が薄暗いトンネル、或いは崩れた坑道を通過する時に、後ろから彼を襲うことを企んだ。 しかし実際のところ、この荒山だけでも、彼を葬るには十分であった。 傷を負った金七十二郎は絶壁の細い道に沿って艱難に歩いた。 それと同時に、枯れた松の木がある崖に、彼を見つめる小さな影が二つあった。 「もう勝ち負けは決まっている。このまま放っておいても奈落に落ちて死ぬだろう。」 痩せこけた婆が言った。 彼女は青く冷たい瞳をしていた。その目には殺気がこもっており、まるで山に潜む毒蛇のようだった。 「いかん!」 彼女のとなりで、太った爺の声が鐘のように響いた。 「あいつは屠毘荘で三百六十三の命をとった、門番の犬まで彼に…」 「屠毘荘主から傷を負ったとは言え、油断してはいかん!」 「フン…」 婆はあっという間に森の中へ消え去った。 「……」 爺も片跛になった剣客を暫く見つめると、腹を触りながらその場を立ち去った。 その道を行く途中、草には一本も触れなかった。 突然空が暗くなり、雨が降り始めた。 雨の中、金七十二郎は剣を杖にして山道を歩いた。 結局、失血と寒さに耐えられなかった彼は岩の上に倒れてしまった。 闇に飲み込まれる前、彼の前には薄水色の裙が… 懐かしい光景だった。 |
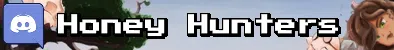



Kinda feels like lunar crystalize Escoffier tbh. Off field dmg, res shred, healing. A good support/...